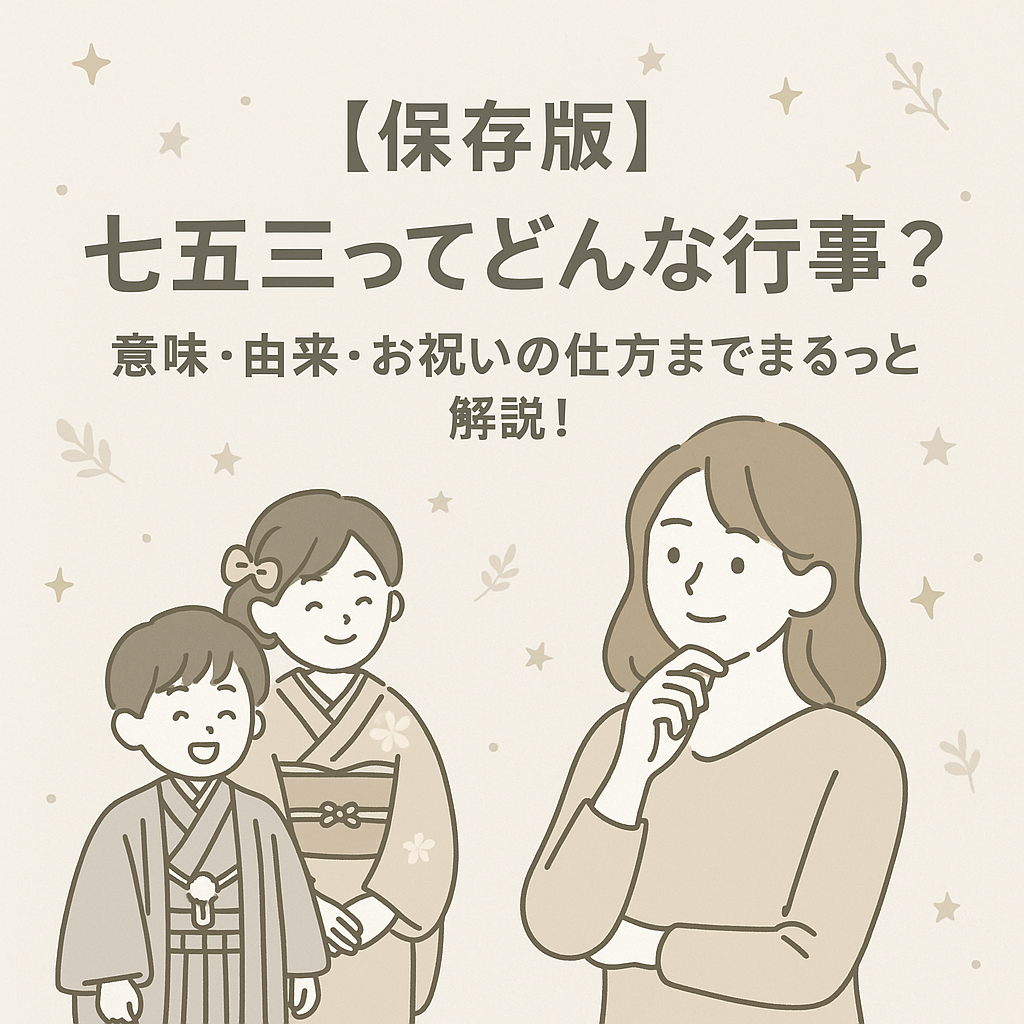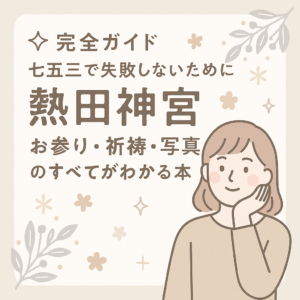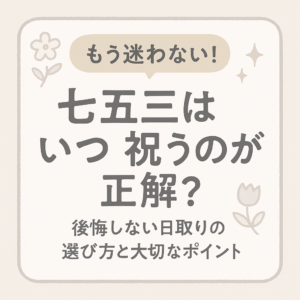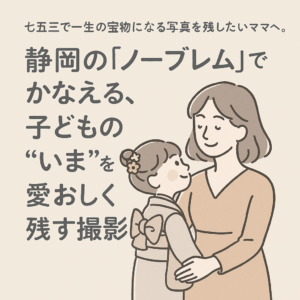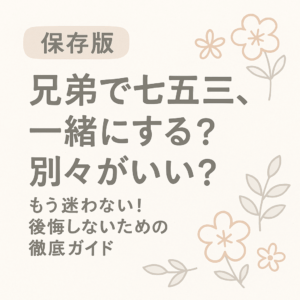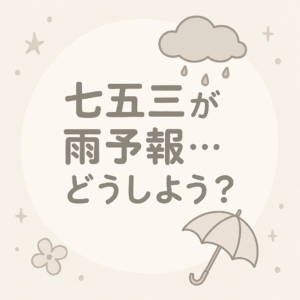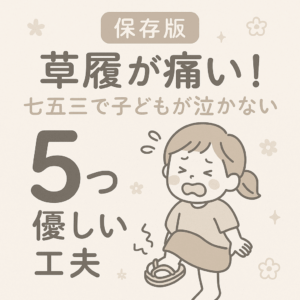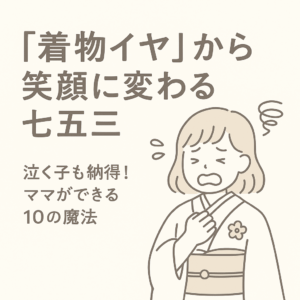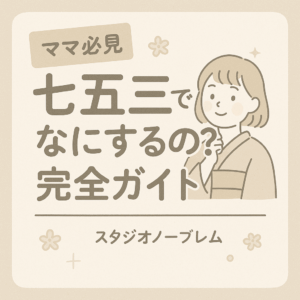「七五三って聞いたことはあるけど、実はちゃんと意味を知らない…」
「お祝いはしたいけど、どう準備すればいい?」
そんなママたちへ。
七五三は、子どもの成長を願うとても大切な行事です。3歳、5歳、7歳という節目の年齢で、神社にお参りをして、これまで元気に育ってくれたことに感謝し、これからもすこやかに成長してほしいと願いを込めます。
この記事では、
・七五三ってそもそも何?
・なぜ3歳、5歳、7歳でお祝いするの?
・いつ、どこで、どうやってお祝いするの?
・準備するものや当日の流れは?
…という基本のキから、細かいポイントまで、丁寧にわかりやすくお伝えします。
はじめて七五三を迎えるママも、これを読めばもう迷わない。
家族みんなで素敵な思い出を作れるよう、しっかりサポートします。
七五三ってどんな行事?
七五三は、簡単にいうと「子どもの成長をお祝いする行事」です。
毎年11月15日前後に、神社へお参りをして、
「ここまで元気に育ってくれてありがとう」
「これからも健やかに大きくなりますように」
と神さまに報告し、お願いをします。
昔の日本では、赤ちゃんが無事に育つことは当たり前ではありませんでした。今のように医療が発達していなかった時代、病気や事故で小さな命が失われることが多かったのです。
だからこそ、3歳・5歳・7歳という「成長の節目」に、ここまで大きくなった喜びと感謝の気持ちを、きちんと神さまに伝える。その気持ちが七五三の始まりです。
なぜ「3歳・5歳・7歳」でお祝いするの?
実は、3歳・5歳・7歳という年齢には、それぞれ意味があります。
これは平安時代から続く日本の伝統的な習わしがもとになっています。
| 年齢 | 性別 | お祝いの意味 |
|---|---|---|
| 3歳 | 男の子・女の子 | 髪を伸ばし始める「髪置き」 |
| 5歳 | 男の子 | 初めて袴を着る「袴着」 |
| 7歳 | 女の子 | 帯を締める「帯解き」 |
■ 3歳「髪置き(かみおき)」
昔の日本では、赤ちゃんは髪を剃って育てることが多く、3歳になって初めて髪を伸ばし始めるタイミングが「髪置き」とされていました。これが3歳のお祝いの由来です。
■ 5歳「袴着(はかまぎ)」
5歳の男の子が初めて袴を着る儀式です。袴を着ることは「社会の一員として認められる」という意味を持っていました。
■ 7歳「帯解き(おびとき)」
7歳の女の子は、着物に付け紐ではなく大人と同じ帯を締めるようになります。この帯を結ぶ儀式が「帯解き」。少しずつ大人の仲間入りをする大切な節目です。
このように、それぞれの年齢には「成長のステップ」としての意味が込められています。
七五三の起源と歴史
七五三のルーツは、なんと平安時代にまでさかのぼります。
当時の宮中や武家の間では、子どもの成長を祝うための儀式が行われていました。
特に江戸時代、徳川家光の長男(後の五代将軍・徳川綱吉)の健康を願って11月15日にお祝いをしたことから、「11月15日=七五三のお祝いの日」として広がったと言われています。
今では地域によってお参りの時期は少し前後することもありますが、11月15日前後に行うのが一般的です。
七五三は何歳で祝うの?数え年?満年齢?
「数え年」とは、生まれたときが1歳、その後お正月を迎えるごとに1歳ずつ年を重ねる考え方。
「満年齢」は、誕生日を迎えて年齢が増える、今の一般的な数え方です。
昔は「数え年」で行うのが主流でしたが、最近は「満年齢」でお祝いするご家庭も増えています。
どちらでも問題ありませんが、兄弟姉妹で一緒にお祝いしたい場合や、子どもの成長具合を見て決めることが多いようです。
七五三のお祝い方法と準備
1. 神社へお参り(七五三詣で)
まずは神社へお参りします。
地元の氏神様(住んでいる土地を守る神さま)にお参りする方もいれば、有名な大きな神社を選ぶ方もいます。
【ポイント】
・祈祷を受ける場合は予約が必要な神社も多い
・お参りだけでもOK(必ずしも祈祷はしなくても大丈夫)
・家族みんなで晴れ着を着て写真を撮ると、記念になります
2. 晴れ着の準備
・3歳の女の子 → 被布(ひふ)付きの着物
・5歳の男の子 → 袴
・7歳の女の子 → 帯付きの着物
最近はレンタルの着物セットがとても充実していて、着付けやヘアセットまでトータルでお願いできるスタジオも増えています。
おじいちゃんおばあちゃんを招いて、みんなで写真撮影をするご家庭も多いですよ。
3. 千歳飴(ちとせあめ)
七五三といえば細長い「千歳飴」。
千歳飴には「細く長く、健康で幸せな人生を歩めますように」という願いが込められています。
紅白の飴が縁起の良い袋に入っていて、袋には鶴や亀、松竹梅など長寿を表す絵柄が描かれています。
「おめでとう」と言いながら渡すと、子どもたちもとても嬉しそうです。
七五三のお祝い、いつから準備する?
お参りの日を決める → 着物を決める → 祈祷の予約 → 写真撮影の日程調整
という流れで、理想は1〜2か月前から準備を始めると安心です。
最近は、混雑を避けるために「10月〜11月の好きな日」にお参りするご家庭も多いので、あまり日にちにとらわれすぎなくても大丈夫。
まとめ|七五三は「家族の絆を深める大切な時間」
七五三は、単なる行事ではありません。
子どもの「ここまで大きくなったね」という成長の証であり、
「これからも元気に、笑顔で過ごしてね」という家族みんなの願いを込めた、特別な一日です。
忙しい毎日だからこそ、こうして立ち止まって、
子どもの笑顔と今この瞬間をしっかり心に刻む。
そんな素敵な時間になりますように。