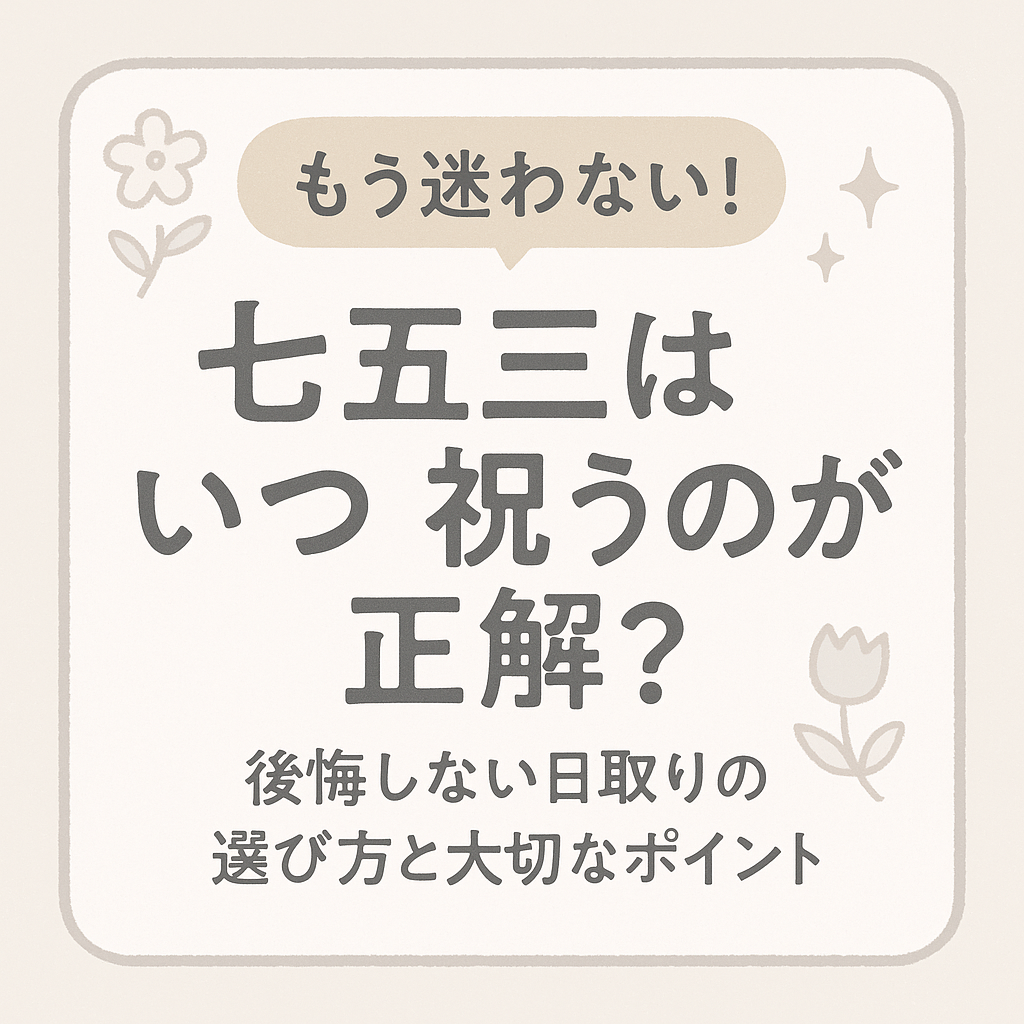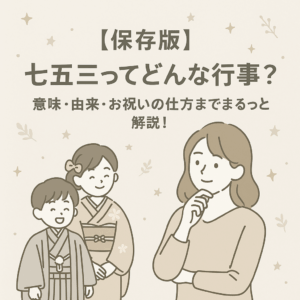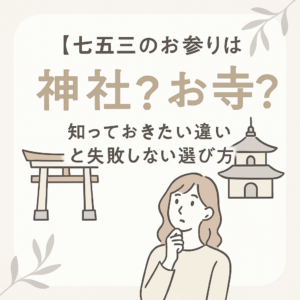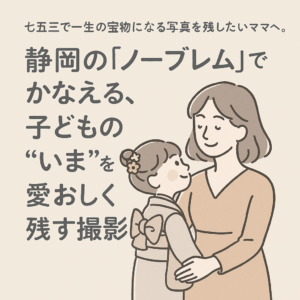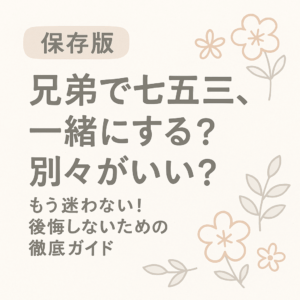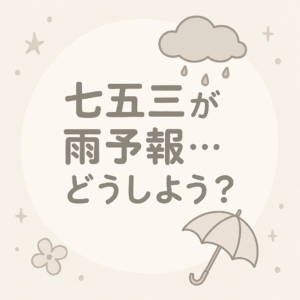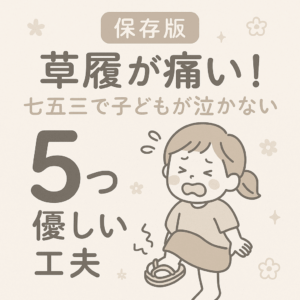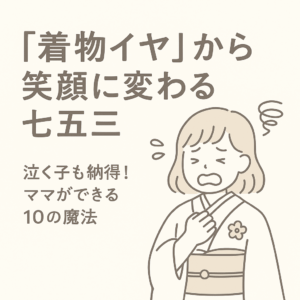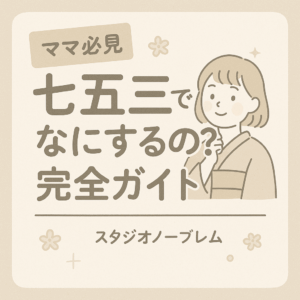「七五三って、いつやればいいの?」
「11月15日がいいって聞いたけど、混んでるって本当?」
「大安の日を選ぶべき?それとも家族の予定優先?」
はじめての七五三、または久しぶりのお祝い。
大切なお子さんの成長を祝う一日だからこそ、ベストなタイミングで思い出を残したいですよね。
でも実は、七五三に“絶対にこの日!”という決まりはありません。
この記事では、七五三の時期や日取りの決め方について、初めての方でも分かりやすいように、じっくり丁寧にお伝えします。
読んだあとには、きっと「この日にしよう!」とスッキリ決められるはず。
ぜひ参考にしてくださいね。
七五三はいつ?正式な日程と、今どきの事情
七五三といえば「11月15日」というイメージが強いですよね。
これは江戸時代、徳川綱吉が自分の息子の健康を祈った日が由来とされています。
ただ、昔と今では生活スタイルが大きく違います。
平日がお休みのご家庭もありますし、共働きでスケジュールを合わせるのが難しいことも多いですよね。
そのため、最近は「10月中旬〜11月下旬」の間で都合の良い日を選ぶご家庭がほとんど。
11月15日にこだわる必要はありません。
むしろ、日程を自由に決められる今だからこそ、
家族みんなが気持ちよく参加できるタイミングを選ぶことが大切なんです。
後悔しない七五三の日取りの選び方
1. まずは、家族みんなのスケジュールを確認!
七五三は、お子さんだけの行事ではありません。
「おじいちゃんおばあちゃんも呼びたい」
「パパのお休みに合わせたい」
「兄弟の学校や習い事の予定もあるし…」
家族の予定を最優先にして、全員が無理なく集まれる日を探しましょう。
特に遠方から親戚を呼ぶ場合や、きょうだいがいる場合は、早めに相談しておくと安心です。
2. 混雑が苦手なら…平日や午前・夕方が穴場!
七五三シーズンの土日祝日は、どこの神社も写真スタジオも予約がいっぱい。
「せっかくの晴れ着なのに、人だらけでバタバタしてしまった…」なんて声も。
そこでおすすめなのが【平日】や【早朝・夕方】の時間帯。
とくに午前中は、お子さんも機嫌がよく、光の加減もきれいなので写真映えもばっちり。
また、夕方の時間帯はスタジオの予約も取りやすく、
「夕焼けを背景にした写真がすごく素敵だった」というママたちの声もあります。
もし可能なら、平日も視野に入れてみると、ゆったりと過ごせる七五三になりますよ。
3. 「大安」は本当に選ぶべき?六曜(ろくよう)の考え方
カレンダーでよく見かける「大安」「仏滅」「友引」などの文字。
これは「六曜(ろくよう)」といって、その日の運勢を表すもの。
特に「大安」は「何ごとにも吉」とされ、結婚式やお祝いごとに人気の日です。
そのため、どうしても大安は予約も混みがち。
ただし、これもあくまで昔からの目安。
大切なのは「みんなが笑顔で参加できる日」。
無理に大安を選ばず、お子さんの体調や家族の都合を優先してOKです。
それでも気になる方は、「先勝(せんしょう)」の午前、「友引(ともびき)」なども選択肢に入ります。
七五三の前撮り・後撮りも考えてみて
「当日はお参りだけにして、写真は別日にゆっくり撮りたい」
「秋は仕事も忙しいから、少し時期をずらしたい」
そんな方におすすめなのが【前撮り】や【後撮り】。
前撮り(4月〜10月)
- 混雑が少なく、スタジオの予約も取りやすい
- 着物の種類も豊富
- 気候が安定していて過ごしやすい
後撮り(12月〜翌年3月)
- 七五三シーズンを過ぎて落ち着いた時期
- 年末年始の帰省に合わせて家族写真が撮れる
「せっかくなら、家族写真も一緒に撮りたい」
「きょうだいの誕生日と合わせてお祝いしたい」
そんな希望も、前撮り・後撮りなら叶えやすくなります。
まとめ:いちばん大切なのは「無理をしない」こと
七五三は、お子さんの成長を願う大切な行事。
でも、決して「義務」ではありません。
お参りの日も、写真撮影の日も、
一番大事なのは【みんなが笑顔で過ごせること】。
「この日でよかったね」
「楽しい思い出になったね」
そう思える一日になるように、日取りは自由に選んで大丈夫。
ぜひ、お子さんと家族にとって最高の七五三を迎えてくださいね。