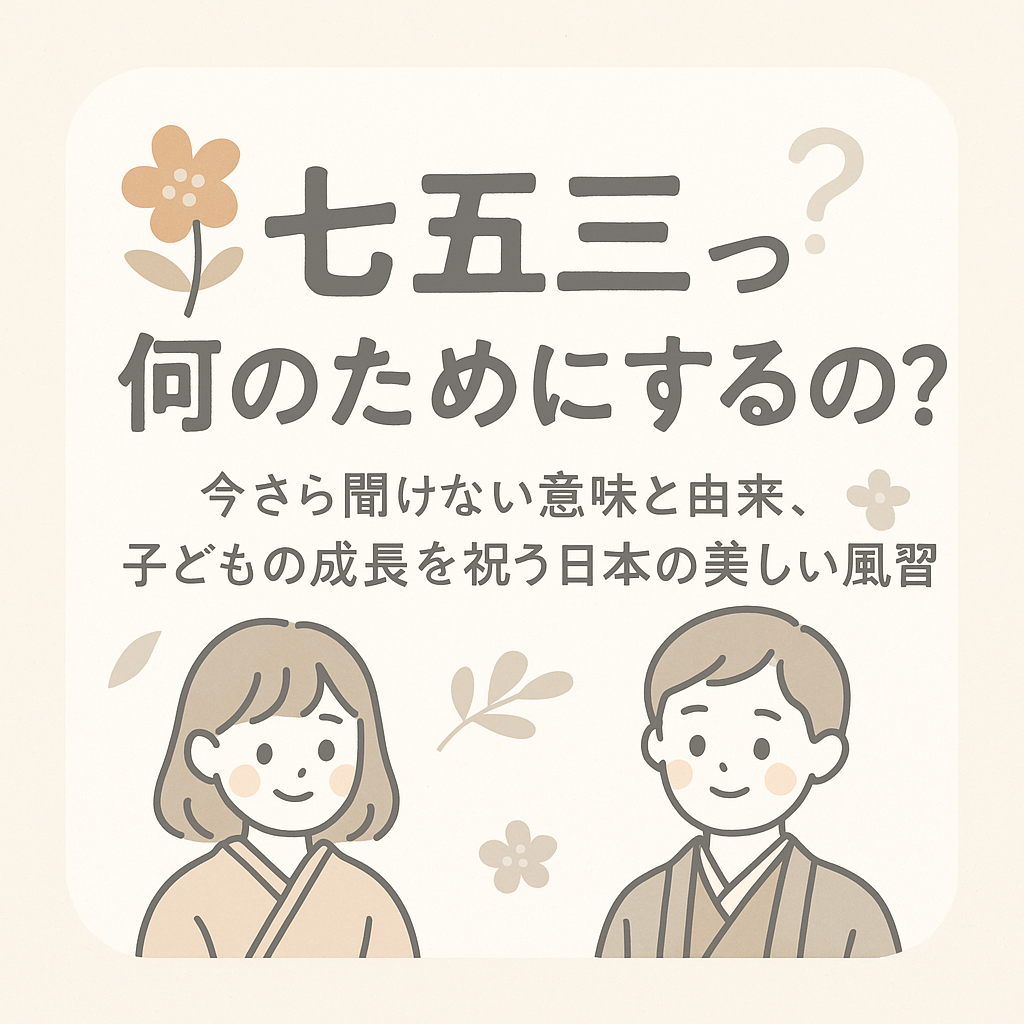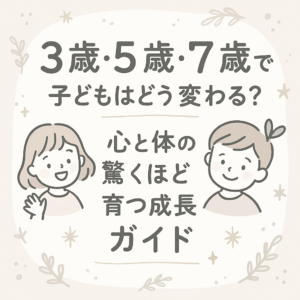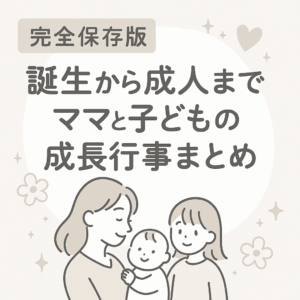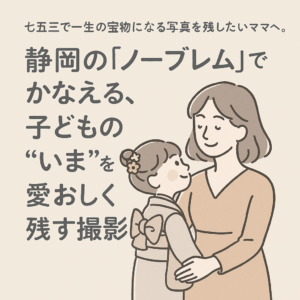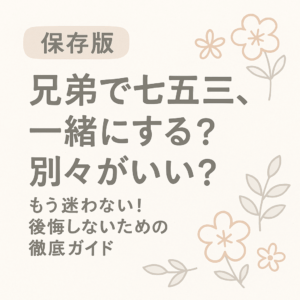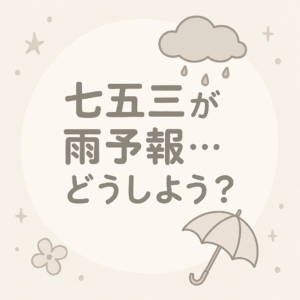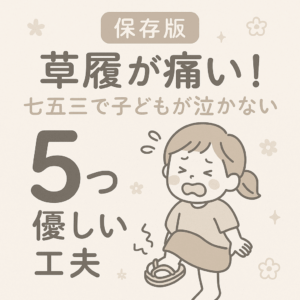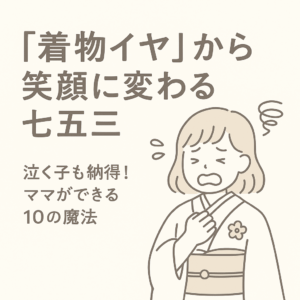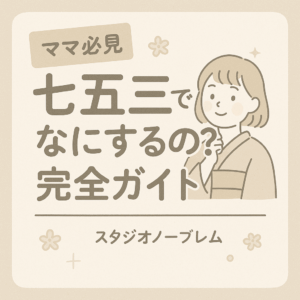子どもが健やかに成長すること。それはすべての親にとって何よりの願いですよね。
でも、ふとしたときに「七五三って、そもそもどういう意味があるんだろう?」と思ったことはありませんか?
この記事では、七五三の歴史や成り立ち、年齢ごとの意味、現代での祝い方までを、ひとつひとつ丁寧にわかりやすくご紹介します。
初めての七五三を迎えるママも、下の子に備えているママも、きっと読み終わったあとには「やってあげてよかった」と思える温かな気持ちになれるはずです。
七五三とは?──子どもの成長を節目に祝う、日本ならではの伝統行事
「七五三(しちごさん)」は、3歳・5歳・7歳という節目の年齢を迎えた子どもの成長を祝い、健やかな将来を願うために行う伝統行事です。
現在では毎年11月15日を中心に、神社へお参りをしたり、写真を撮ったり、お祝いの食事を囲んだりする形で祝われています。ですがその由来は、実は1000年以上も前にさかのぼります。
七五三の起源──平安・室町・江戸時代に根付いた成長の儀式
七五三は、もともとは宮中や武家の間で行われていた「成長の儀式」が元になっています。かつては医療や衛生の発達していない時代、子どもが無事に育つことはとても尊いことでした。そのため、一定の年齢に達したときに「ここまで育ってくれてありがとう」「これからも健やかに育ちますように」という気持ちを込めて、成長の区切りごとに祝っていたのです。
● 3歳「髪置(かみおき)」──髪を伸ばし始める節目
平安時代、子どもは産まれてから3歳までは髪を剃って育てる風習がありました。3歳になる春から、ようやく髪を伸ばし始めることが許され、そのタイミングで「髪置(かみおき)」という儀式が行われました。白い綿で作った髪を頭にのせ、「白髪になるまで長生きしますように」と願いを込めて祝ったのが起源です。
この名残から、現代の七五三でも男女ともに3歳でお祝いをします。
● 5歳「袴着(はかまぎ)」──初めての袴、男の子としての自覚
5歳になると、男の子は初めて袴を着けて正式な衣服を身につける儀式を行いました。これが「袴着(はかまぎ)」です。碁盤の上に乗り、吉方を向いて袴を着るという儀式には、「男として一人前の道を歩き始める」という意味が込められています。
今もなお、5歳の男の子が紋付き袴姿で神社にお参りする風景は、日本の秋の風物詩となっています。
● 7歳「帯解(おびとき)」──幼児から少女へ
7歳の女の子は、それまで着ていた紐付きの着物から卒業し、大人と同じように「帯」で着物を締めるようになります。この節目を祝う儀式が「帯解(おびとき)」です。社会的にも一歩大人に近づいた証として、晴れ着をまとい、家族や親族で成長を喜び合います。
七五三はいつやるの?──「11月15日」の理由
七五三は毎年「11月15日」に行うのが正式とされていますが、この日程にも理由があります。江戸時代の将軍・徳川綱吉が、わが子の健康を祈ってこの日に祝ったことから広まり、庶民にも定着しました。
ただし、現代では必ずしも11月15日にこだわらず、10月〜11月の間の都合のよい日を選ぶご家庭が多いです。神社への参拝や写真撮影、親族との食事など、家族のスタイルに合わせて柔軟に祝えるのも七五三の魅力です。
数え年?満年齢?──どちらでもOK
七五三を「数え年」でやるのか、「満年齢」でやるのか、悩む方も少なくありません。結論から言えば、どちらでも大丈夫です。昔は数え年が主流でしたが、最近では実年齢に合わせて、子どもの成長に無理のないタイミングで祝うご家庭が増えています。
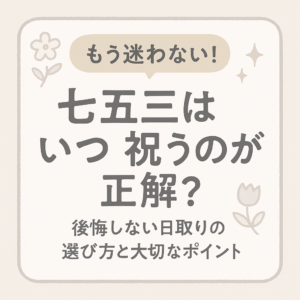
七五三は、家族の絆を確かめる大切な時間
七五三は、単なるイベントではありません。子どもが無事にここまで育ってくれたことを喜び、その成長に感謝し、これからの健やかな未来を願う――そんな日本ならではの温かな文化です。
家族で神社を歩いたこと、着物を着て笑い合ったこと、記念写真に残したあの一日。そのすべてが、お子さまの心に「愛された記憶」として残っていくことでしょう。
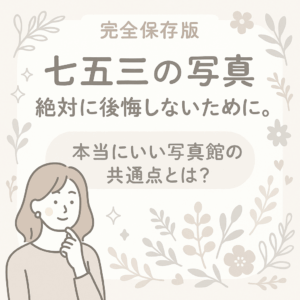
思い出に残る七五三のために──スタジオノーブレムのご案内
スタジオノーブレムが選ばれる理由
- 自然な表情を引き出すプロの技術
- 子どもがリラックスできる優しい撮影空間
- 着物・ドレス・ヘアセットまで全部おまかせOK
- ご家族写真も一緒に残せる充実プラン
スタジオノーブレムは、写真を「飾るだけのもの」ではなく、
“家族の記憶”を閉じ込める一枚として大切に残します。
「こんな顔、今しか見られないね」
そんな言葉が思わずこぼれる、やさしい時間を一緒に。