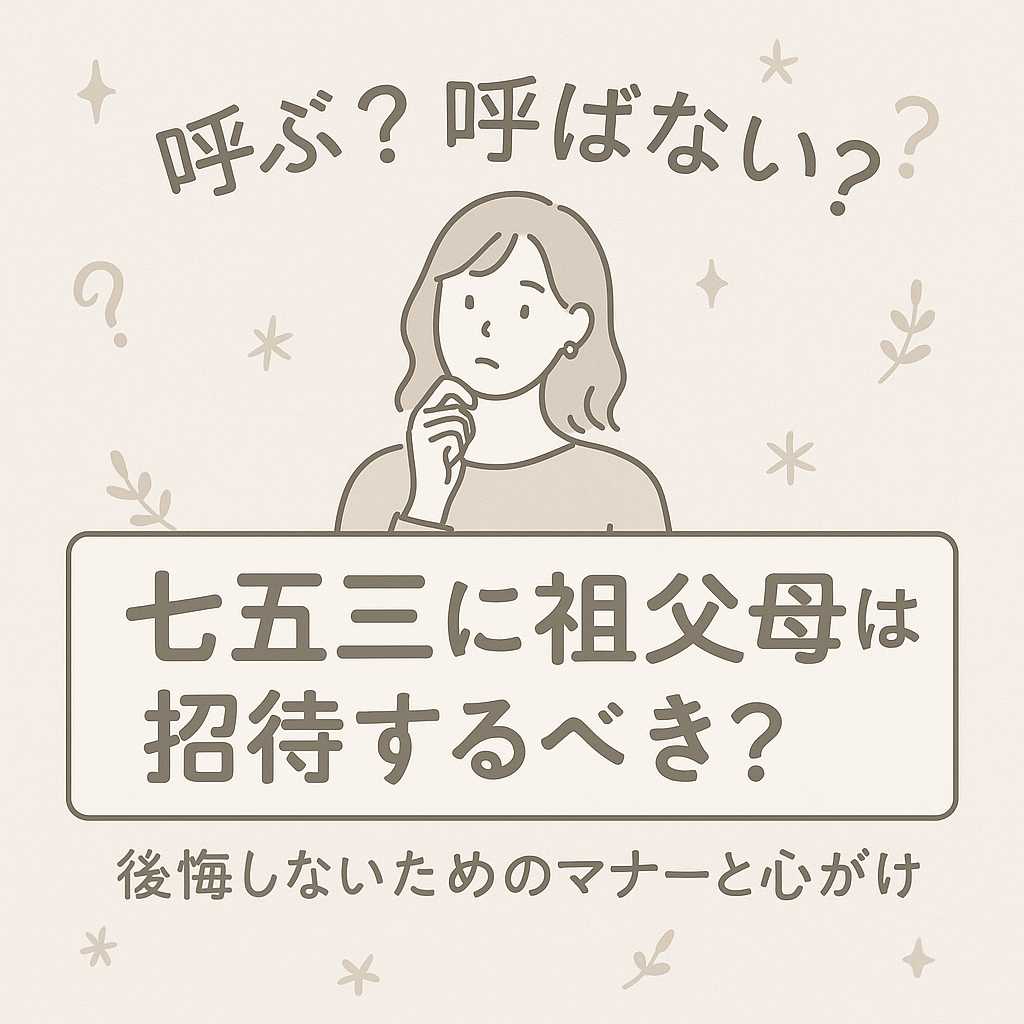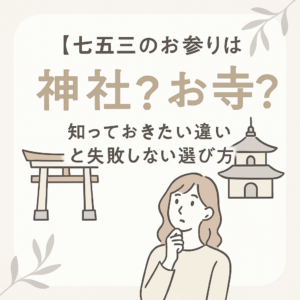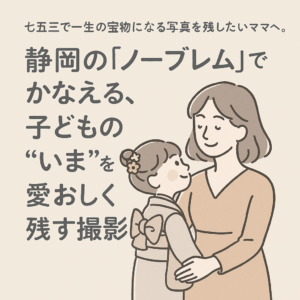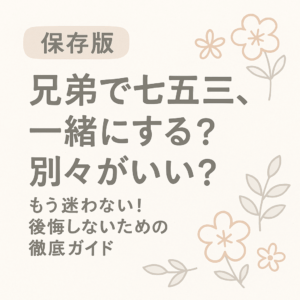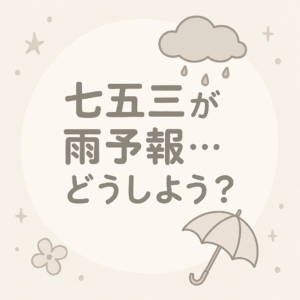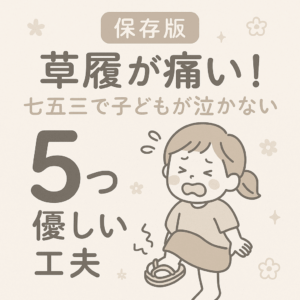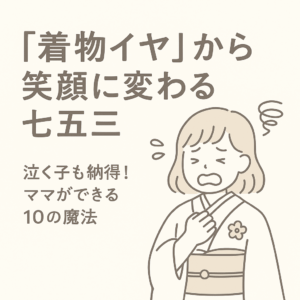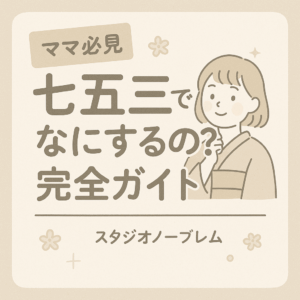七五三は、わが子の成長を祝い、感謝の気持ちを込める大切な節目。
「ここまで元気に大きくなってくれてありがとう」──そう思いながら、晴れ姿を楽しみにしているママやパパも多いのではないでしょうか。
でも、いざお祝いを考えると悩むのが、**「祖父母を呼ぶべきかどうか」**ということ。
「両親(おじいちゃんおばあちゃん)にも晴れ姿を見せたい気持ちはある。でも、もし来てもらうならどうすれば失礼がないんだろう?」
「逆に呼ばないのって失礼かな…?」
そんなふうに迷う方はとても多いんです。
この記事では、
- 祖父母を呼ぶメリット
- 招待するときに気をつけたいマナー
- 逆に呼ばない場合の心くばり
この3つをわかりやすく、できるだけ具体的にお伝えします。
「知らなくて後悔した…」なんてことにならないように。
読んでいただいたあなたが、気持ちよく七五三を迎えられるお手伝いができたらうれしいです。
■ そもそも七五三は家族だけでいいの?
まずはじめに、「祖父母を必ず呼ばないといけない」という決まりはありません。
最近は、
- パパ・ママと子どもだけでお参りする
- 祖父母にも参加してもらう
どちらのパターンもあります。
どちらが「正しい」ではなく、**「そのご家族にとって心地よい形」**が一番大切です。
でももし祖父母を招待することで、
- 祖父母がとても喜んでくれる
- 子どももおじいちゃんおばあちゃんと写真を撮れてうれしい
- 家族みんなでお祝いの気持ちを共有できる
──そういったことが期待できるなら、ぜひ一度「どうする?」と話し合ってみるのがおすすめです。
■ 祖父母を招くときの5つのマナーと気をつけたいこと
① できるだけ早めに声をかける
七五三の時期は10月〜11月頃。とくに土日祝日は神社も写真館も混み合います。
祖父母世代も、意外と予定が埋まっていることもあります。
「○月○日に七五三のお参りをしようと思ってるんだけど、一緒に来てもらえたらうれしい」
そんなふうに、余裕を持って早めに相談するのが◎。
② 両家のバランスに気をつける
たとえば「パパのご両親だけ誘ったけど、ママの両親は呼ばなかった」という場合、あとでちょっと気まずくなってしまうケースも。
両家とも呼ぶのが理想ですが、難しい場合は「今回は家族だけでお祝いする予定」と最初に説明をしておくと、トラブルになりにくいです。
もしどちらかの祖父母しか参加できない場合でも、
「お写真はあとでお送りしますね」
「また別の機会にお顔を見せに行きますね」
といったフォローがあると、より印象が良くなります。
③ お祝い返し(内祝い)の準備も忘れずに
祖父母が当日お祝いを持ってきてくれることもあります。
金額は家庭によってさまざまですが、3,000円〜1万円ほどのお祝いをいただくケースが多いです。
お返しとして、
- 菓子折り
- おしゃれなタオルセット
- 記念写真を添えたアルバム
などを用意しておくと喜ばれます。
最近は、当日の様子をまとめた「フォトブック」も人気。
心のこもったお返しは、もらった方も温かい気持ちになります。
④ 祖父母の体調や移動の負担に配慮する
七五三は、朝から着付け、写真撮影、お参り、食事会…と、意外と忙しくなりがち。
祖父母の年齢や体調を考えて、長時間の移動や待ち時間はできるだけ避けましょう。
移動が負担にならない場所や時間帯を選んだり、食事会も無理のない範囲で行ったりすると、みんなが楽しく過ごせます。
⑤ 記念写真は家族全員で
せっかく集まったなら、ぜひ祖父母も一緒に記念写真を。
スタジオ撮影の場合は予約が必要なので、人数を事前に伝えておきましょう。
お参りの際のスナップ写真でも、おじいちゃんおばあちゃんと手をつないだり、ぎゅっと抱っこしてもらったりするカットは、あとから見返しても心温まります。
■ もし祖父母を呼ばない場合は?
事情があって祖父母を招待できないときも、感謝の気持ちを伝える方法はいろいろあります。
たとえば…
- 当日の写真を送る
- 子どもから「ありがとう」と書いたメッセージカードを渡す
- 動画メッセージを撮って送る
「来てもらえなくてごめんね」ではなく、
「こうして無事に七五三を迎えられたこと、いつも見守ってくれてありがとう」
そんな前向きな伝え方がポイントです。
■ 七五三は家族みんなでお祝いする、特別な日。
どんな形であっても、大切なのは「おめでとう」の気持ちを伝えること。
祖父母を招くかどうかは、ご家族それぞれの考え方や事情で決めて大丈夫です。
無理に気をつかいすぎて疲れてしまうより、
「うちの子のために、どんなお祝いがいちばんいいかな?」
「おじいちゃんおばあちゃんに、どうしたら気持ちよく参加してもらえるかな?」
と、心から考えて行動することが何より素敵なお祝いになります。
この先も、七五三の思い出が、家族の宝物になりますように──。